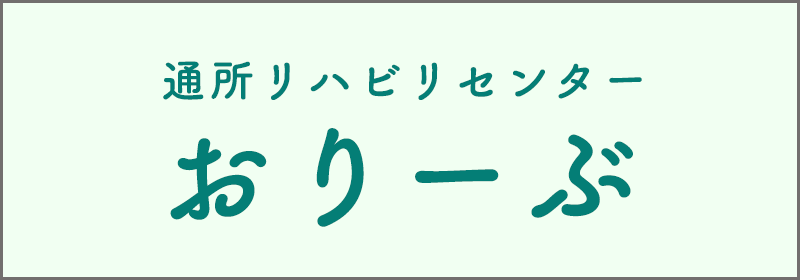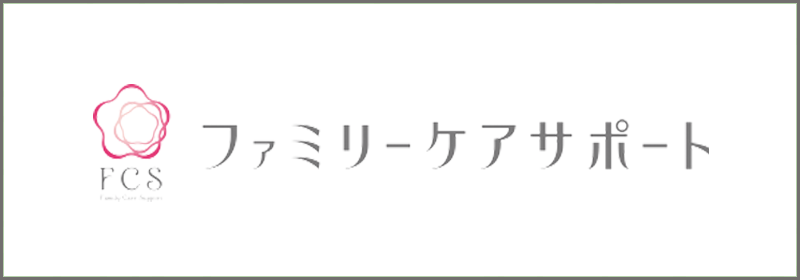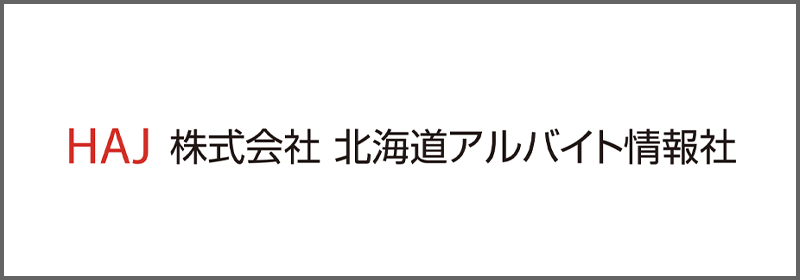「この記録、誰が見ても“佐藤さんらしさ”が伝わるようにしたいんです」
沙耶がそう語ったとき、職員たちは静かにうなずいた。
記録は、ただの情報ではない。
それは、“その人の人生の断片”であり、“ケアの根拠”であり、
そして何より、“尊厳を守る器”だった。
法人では、記録の管理体制が制度的に整備されていた。
記録の保存期間、閲覧権限、情報漏洩防止策、電子記録のセキュリティ。
監査対応や第三者評価にも耐えうる仕組みが構築されていた。
しかし沙耶は思った。「管理とは、守ること。
そして守るべきは、“情報”ではなく、“その人の尊厳”なのだ」
彼女は「記録を守る文化づくりプロジェクト」を立ち上げた。
目的は、記録管理を“制度の遵守”ではなく、“信頼の継続”として根づかせること。
まず始めたのは、「記録の意味を語る会」。
職員が「記録を書くとき、何を意識しているか」「誰のために書いているか」を語り合う場。
ある職員はこう語った。
「記録は、未来の職員への手紙だと思って書いています。
“この人は、こういう関係性を大切にしていた”って伝えたいんです」
次に、「記録の保管と閲覧の透明化」を進めた。
- 閲覧履歴の記録
- 利用者本人への開示ルールの整備
- 情報共有の目的と範囲の明示
これにより、「誰が、何のために、どの記録を見るか」が明確になり、
“記録の信頼性”が高まった。
ある日、佐藤さんがこう語った。
「私のことが、ちゃんと記録されてるって思えると、
ここで過ごす時間が“自分の人生の続き”になる気がするんです」
沙耶はその言葉に、記録管理の本質を見た。
それは、“制度の整備”ではなく、“関係性の継続”だった。
評価項目【45 Ⅲ-2-(3)-②――「利用者に関する記録の管理体制が確立している」。】
それは、「“体制があるか”ではなく、“記録が尊厳を守る器として機能しているか”が問われる。」
沙耶は記録の余白にこう書いた。
「今日、佐藤さんが“ここで過ごす時間が、私の人生の続きになる”と言った。
その一言が、記録管理の成果だと思う」
記録とは、制度の履歴ではない。
それは、“その人の物語”を未来につなぐ器。
そしてその器が、ケアの現場に“尊厳と信頼”を根づかせていくのだ。
沙耶は、評価項目の束を机に広げながら、静かに目を閉じた。
この一年、彼女は制度の言葉を“現場の温度”に訳す旅を続けてきた。
それは、チェックリストを超えて、“問い”として立ち上がる営みだった。
福祉施設の機能を地域に還元するとは、
専門性を閉じ込めるのではなく、“暮らしの知恵”として開くこと。
地域の声に応える公益的な活動とは、
制度の使命ではなく、“関係性の応答”であること。
利用者の尊厳を守るとは、
理念を掲げることではなく、“まなざしの質”を育てること。
意思決定支援とは、“選ばせる”ことではなく、“その人らしさに寄り添う”こと。
安心・安全を守るリスク管理とは、
マニュアルの遵守ではなく、“気づきの文化”を育てること。
感染症や災害への備えとは、“命と関係性”を守る実践であること。
標準化とは、手順の統一ではなく、“ケアの哲学”を言語化すること。
その見直しとは、“変化に応答する柔軟な土台”を築くこと。
個別支援計画とは、“その人の物語”を暮らしの設計図にすること。
その評価・再設計とは、“今に寄り添う再構築”であること。
記録とは、業務の履歴ではなく、“尊厳を守る器”。
その管理とは、“信頼の継続”を支える責任。
沙耶は、最後の記録の余白にこう書いた。
「制度は、問いである。
その問いに、現場の言葉で答え続けることが、ケアの哲学だと思う」
そして彼女は、評価項目の束をそっと閉じた。
その瞬間、制度は“紙”ではなく、“物語”になった。
ケアとは、問いから始まる。
その問いに、誰かの声で、誰かのまなざしで、誰かの実感で、
答え続けること。
それが、福祉の本質なのだ。
了
#福祉サービス第三者評価を広げたい