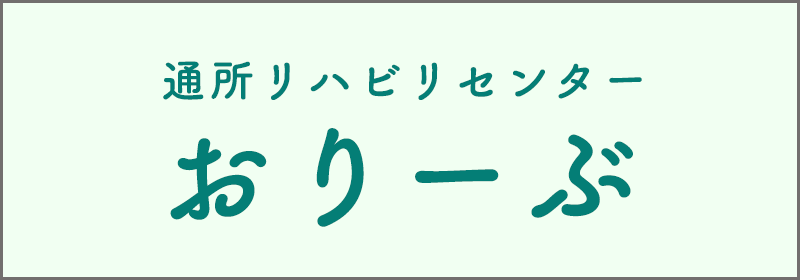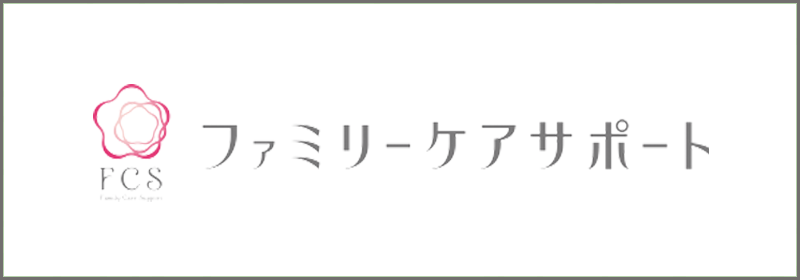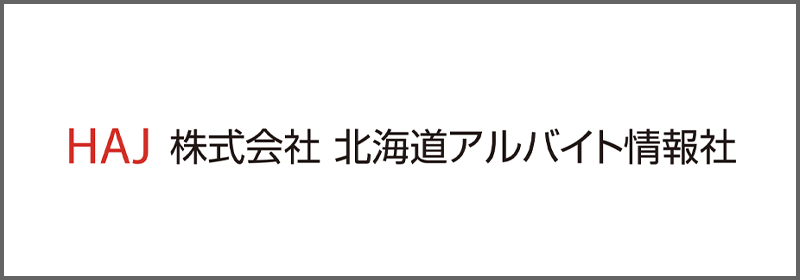「計画って、“支援の枠”を決めるものじゃなくて、“その人の暮らし”を描くものですよね」
沙耶がそう語ったとき、職員たちは静かにうなずいた。
アセスメントは、聞き取りではない。
それは、“その人の物語”を聴くことから始まる。
法人では、個別支援計画の策定手順が整備されていた。
初回アセスメント、モニタリング、半年ごとの見直し、記録様式の統一。
ケアマネジャーとの連携も図られていた。
しかし沙耶は思った。「形式は整っていても、“その人らしさ”が計画に反映されているかは別の話」
彼女は「物語から始める支援計画プロジェクト」を立ち上げた。
目的は、アセスメントを“暮らしの文脈”として捉え、
個別支援計画を“その人の人生の延長線”として設計すること。
まず始めたのは、「物語アセスメントシート」の導入。
従来の「できること・できないこと」ではなく、
- これまでどんな暮らしをしてきたか
- 何を大切にしてきたか
- どんな場面で安心できるか
- どんな言葉が心に残っているか
など、“その人の背景”を丁寧に聴き取る項目を加えた。
ある日、佐藤さんはこう語った。
「若い頃は、毎朝ラジオ体操してたんです。
それが習慣で、やらないと落ち着かなくて」
その言葉をもとに、支援計画には「朝のラジオ体操を日課に組み込む」と記載された。
次に、「計画づくりの対話時間」を設けた。
職員が利用者と1対1で、計画の内容を一緒に確認し、
「この支援、あなたらしいと思いますか?」と尋ねる時間。
その場では、利用者の表情や語りが、計画の質を左右した。
佐藤さんはこう語った。
「“自立支援”って言われると、ちょっとプレッシャーだけど、
“できることを一緒に探す”って言われると、前向きになれるんです」
沙耶はその言葉に、計画の本質を見た。
それは、“支援の枠”ではなく、“関係性の設計”だった。
さらに、職員向けに「アセスメントの読み解き研修」を実施。
- 表面的な情報の奥にある“意味”を探る
- 利用者の語りから“価値観”を抽出する
- 計画に“その人らしさ”をどう反映するか
- 支援の目的を“本人の言葉”で記述する
この研修を通じて、計画が“業務の指針”から“暮らしの地図”へと変化していった。
評価項目【42 Ⅲ-2-(2)-①――「アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している」。】
それは、「“計画があるか”ではなく、“その人の物語が反映されているか”が問われる。」
沙耶は記録の余白にこう書いた。
「今日、佐藤さんが“この計画、私の人生の続きみたいですね”と言った。
その一言が、アセスメントの成果だと思う」
支援計画とは、制度の枠組みではない。
それは、“その人のこれまで”と“これから”をつなぐ設計図。
そしてその設計図が、ケアの現場に“その人らしさ”を根づかせていくのだ。
#福祉サービス第三者評価を広げたい