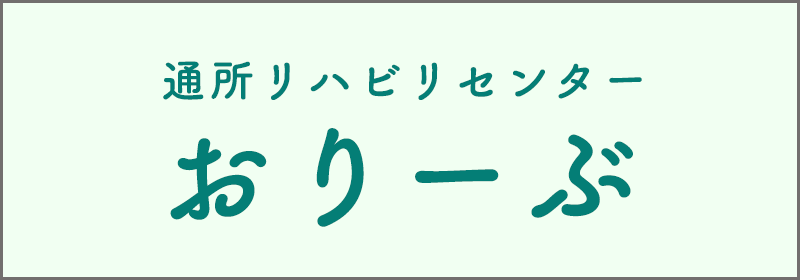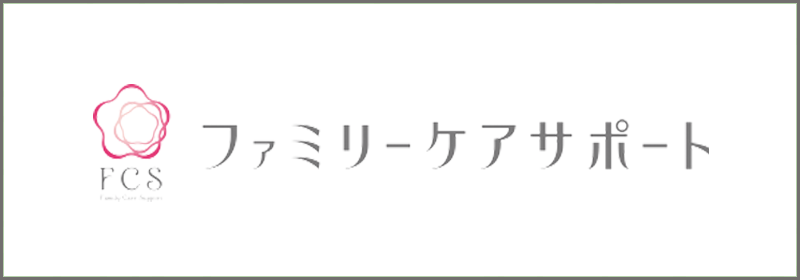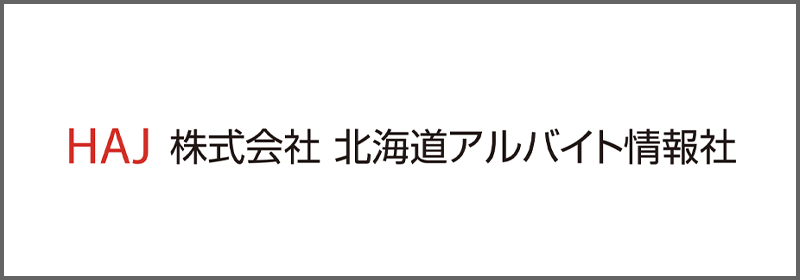「この対応って、前と違う気がするんですけど…」
新人の理佳が、先輩職員のケアを見ながらそうつぶやいた。
同じ利用者、同じ場面。
でも、対応の仕方が微妙に違っていた。
沙耶はその言葉に、ケアの“揺らぎ”を感じた。
法人では、福祉サービスの標準的な実施方法が文書化されていた。
ケアマニュアル、業務手順書、加算対応のガイドライン、記録様式の統一。
定期的な見直しも行われていた。
しかし沙耶は思った。「文書があるだけでは、ケアは揃わない。
“なぜその方法なのか”が共有されていなければ、形だけが残ってしまう」
彼女は「ケアの言葉を育てるプロジェクト」を立ち上げた。
目的は、標準的な実施方法を“現場の納得”として根づかせること。
まず始めたのは、「ケアの理由を語る会」。
職員が、日々のケアの中で「なぜその方法を選んだか」を語り合う時間。
ある職員はこう語った。
「〇〇さんは、食事のときに“声かけの順番”が違うと落ち着かない。
だから、“お箸を渡してからメニューを伝える”ようにしている」
別の職員はこう語った。
「△△さんは、入浴時に“湯温の確認”を自分でしたい。
だから、職員が“温度はどうですか?”と聞くようにしている」
沙耶はそれらの語りをもとに、「ケアの標準化ノート」を再構築。
単なる手順ではなく、“その方法を選ぶ理由”を添えた文書。
それは、マニュアルではなく、“共通言語の集積”だった。
さらに、「標準化のふりかえり研修」を実施。
- 文書化された方法が、現場でどう活かされているか
- 利用者の反応はどうか
- 職員の理解度や納得感はどうか
- 改善すべき点はどこか
この研修を通じて、文書が“現場の実感”と結びついていった。
また、利用者の声も反映する仕組みとして、
「ケアの納得アンケート」を導入。
- 「この対応は、あなたにとって安心できるものですか?」
- 「もっとこうしてほしいと思うことはありますか?」
- 「職員の説明はわかりやすかったですか?」
ある日、佐藤さんがこう語った。
「前に“どうしてこの順番なんですか?”って聞いたら、
“〇〇さんが落ち着けるようにって考えてるんです”って言われて。
それが、すごく嬉しかったです」
沙耶はその言葉に、標準化の本質を見た。
それは、“手順の統一”ではなく、“関係性の質を守る言葉”だった。
評価項目【40 Ⅲ-2-(1)-①――「提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている」。】
それは、「“文書があるか”ではなく、“その文書がケアの質を支えているか”が問われる。」
沙耶は記録の余白にこう書いた。
「今日、理佳が“この方法には理由があるんですね”と言った。
その一言が、標準化の成果だと思う」
標準化とは、手順の統一ではない。
それは、“ケアの質”を守るための共通言語であり、
その言語が、現場の納得と利用者の安心をつなげていくのだ。
#福祉サービス第三者評価を広げたい