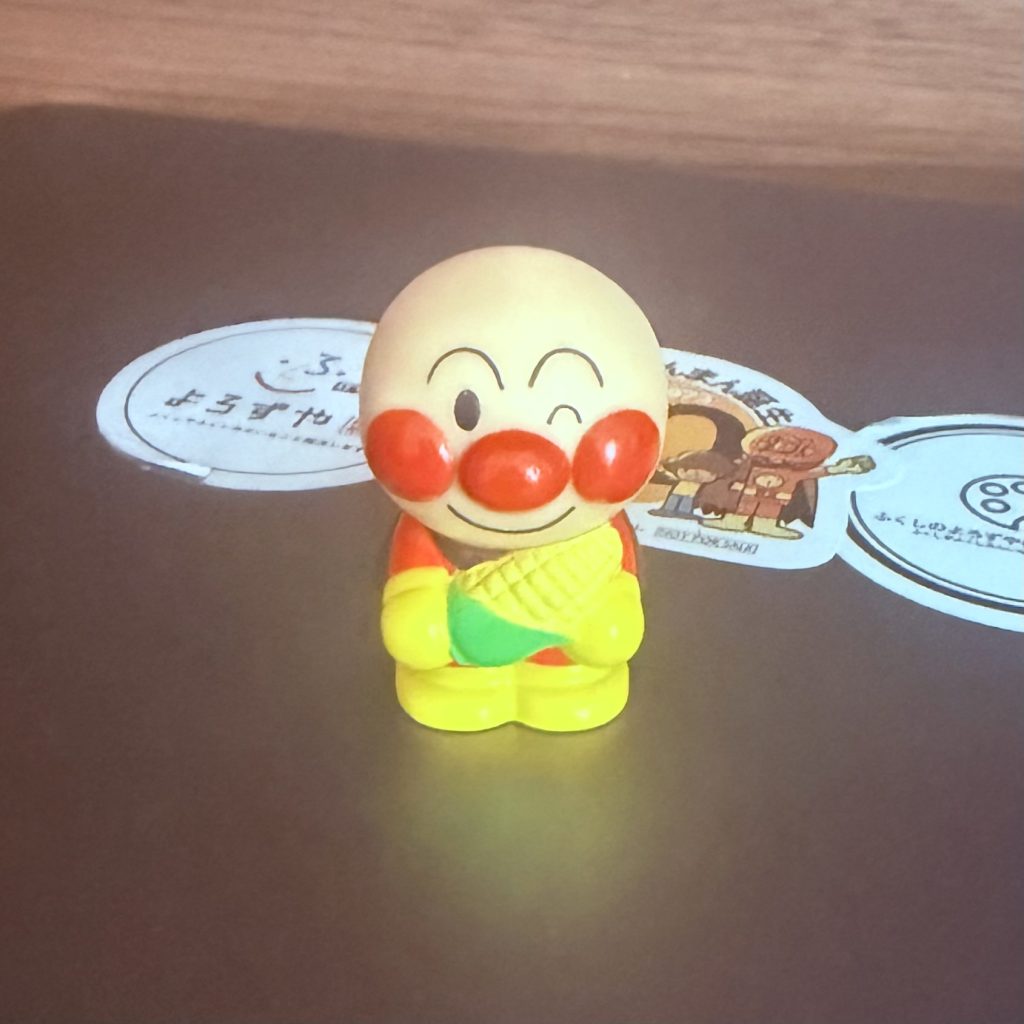介護現場におけるコンプライアンス活動は、利用者さんの安全や信頼を守るための重要な取り組みです。しかし、「ルールを守ることが目的化してしまい、本来のケアの意義が見えづらくなる」という声を耳にすることもあります。そんな時こそ、哲学者アウグスティヌスの「神への愛」や「善と悪」の考え方が、コンプライアンス活動の本質を見直すヒントを与えてくれます。
「カリタス(神への愛)」が生む最高の営み
アウグスティヌスは、「神への愛(カリタス)」こそが人間の最高の営みであり、それが人々を幸福にすると説きました。介護現場では、「カリタス」を利用者さんへの思いやりやケアへの愛と捉えることができます。コンプライアンス活動もまた、この「愛」を基盤にするべきです。「ルールを守ること」だけが目的ではなく、「利用者さんやスタッフが安心して過ごせる環境を作ること」がその本質です。愛を土台に、規範を守る意味を考えることで、コンプライアンスが単なる義務ではなく、職場全体の幸福に繋がるものとして機能します。
「悪は善からの欠如」である
アウグスティヌスは、「悪は実在せず、善が欠けた状態である」と述べました。つまり、悪事やミスは、善意や正しい行いが足りない状態で起こるのです。介護現場でも、不正やルール違反は、「良かれと思ってやった」「忙しさの中でつい…」という背景がある場合が多いものです。ここで重要なのは、「悪を罰する」だけでなく、「善を補い育てる」こと。たとえば、スタッフ一人ひとりが規範の意義や目的を深く理解し、善なる行動を選び取れるよう、教育や共有の場を設けることが大切です。悪を排除するだけでなく、善を育てる文化を作ることが、ルール違反を未然に防ぐ鍵となるでしょう。
原罪とコンプライアンスの視点
アウグスティヌスは、「原罪」が全人類に遺伝すると説きました。これは、人間には本来、弱さや過ちを犯す可能性がある、ということを意味します。介護現場でも、人間である以上、ミスや不注意がゼロになることはありません。だからこそ、コンプライアンス活動では、「過ちを犯さない完璧な職場」を目指すのではなく、「過ちを減らし、正せる仕組みを作る」ことが重要です。スタッフがミスを恐れて萎縮する職場ではなく、間違いに気づき、それを改善できる環境を整えること。これが、実効性のあるコンプライアンス活動を実現するためのポイントです。
まとめ
アウグスティヌスの哲学が示すのは、コンプライアンス活動の本質は「善を育み、愛を基盤とする文化づくり」にあるということです。ルールを形だけ守るのではなく、その背景にある「利用者さんやスタッフの幸福を守る」という目的を見失わないこと。そして、人間としての弱さを受け入れ、それを正せる仕組みを持つこと。この2つが、介護現場におけるコンプライアンスをより意義あるものへと導きます。