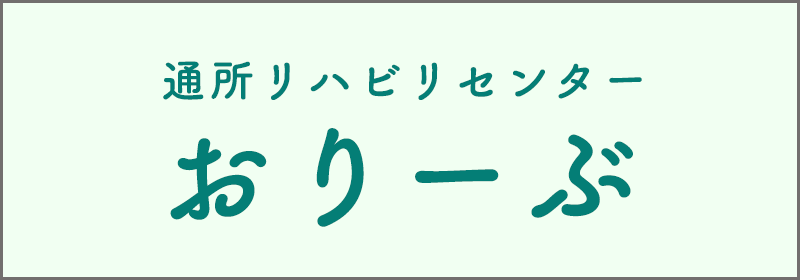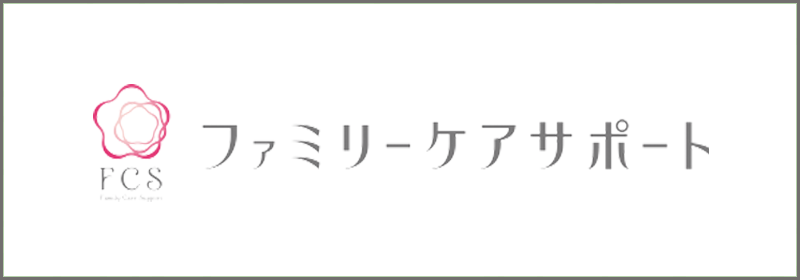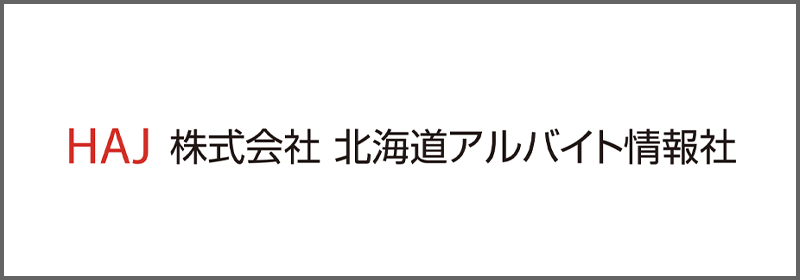介護の現場で、若手職員が積極的に意見を発信することは、職場に新しい視点をもたらし、チーム全体の成長にも繋がります。しかし、「こんなこと言ってもいいのだろうか」「先輩たちの反応が怖い」という気持ちから、なかなか発信できない若手も多いのではないでしょうか?ここで、ジークムント・フロイトの「無意識」や「防衛機制」の考え方を取り入れると、こうした心の動きを理解し、乗り越えるヒントが見つかるかもしれません。
「無意識」が行動を制御している
フロイトによれば、私たち人間の行動には、意識的に理解できない「無意識」の影響が大きく関わっています。若手職員が意見を発信する際、「自分の意見なんて役に立たないのでは?」「失敗したらどうしよう」と感じるのは、無意識の中で「恐れ」や「自己否定感」が働いているからです。しかし、こうした感情は、無意識的な思い込みが生み出していることを認識するだけで和らぎます。「なぜ怖いのか」「何を恐れているのか」を冷静に振り返ることで、発信する勇気を引き出す第一歩が踏み出せるのです。
「イド」「超自我」「自我」のバランスを取る
フロイトは、私たちの心を「イド(欲望)」「超自我(規律)」「自我(調整役)」の3つの要素で説明しました。若手職員が意見を発信しようとする時、例えば「もっとこうした方が良いのでは?」という欲望(イド)が生まれます。しかし同時に、「自分が言うべきではないかもしれない」という規律や制約(超自我)がブレーキをかけることもあります。この時、両者のバランスを取る「自我」が、現実的で納得のいく行動を選ぶ鍵となります。つまり、「自分の意見を伝えることで、利用者さんや職場にどんなプラスがあるか」を具体的に考えることで、行動に移しやすくなるのです。
「防衛機制」に気づき、克服する
フロイトの「防衛機制」とは、不安や葛藤から自分を守るために働く無意識の反応です。たとえば、「発言したいけど、自分なんかが言っても変わらない」と感じるのは、失敗への不安を避けるための「防衛機制」が働いている状態と言えます。しかし、この防衛機制に気づき、「本当にこの不安は現実に基づいているのか?」と問いかけることで、その感情を乗り越える一歩を踏み出すことができます。発信すること自体が、職場にとって新しい風をもたらす大切な役割だと捉える視点を持ちましょう。
まとめ
フロイトの哲学から学べるのは、「無意識」や「防衛機制」に振り回されるのではなく、それらを理解し、うまくコントロールすることで行動を起こせるということです。若手職員が積極的に意見を発信するためには、自分の内面の動きを認識し、行動の目的を明確にしながら、勇気を持って一歩前に踏み出すことが重要です。