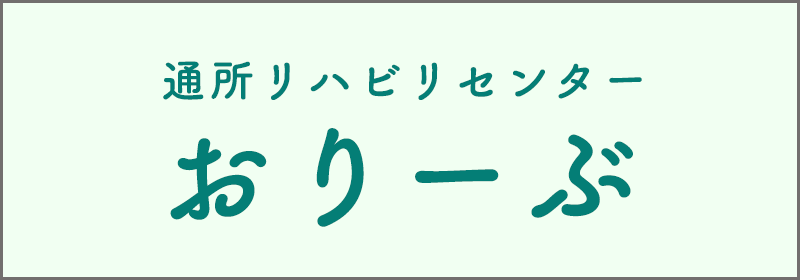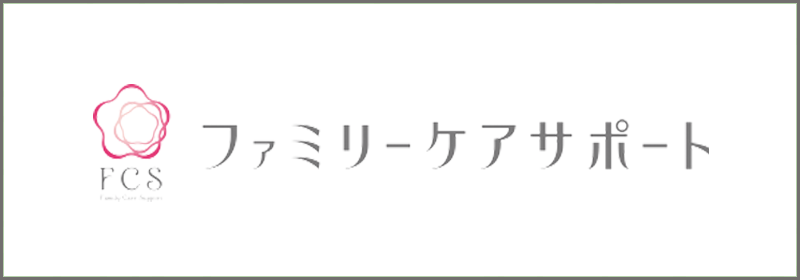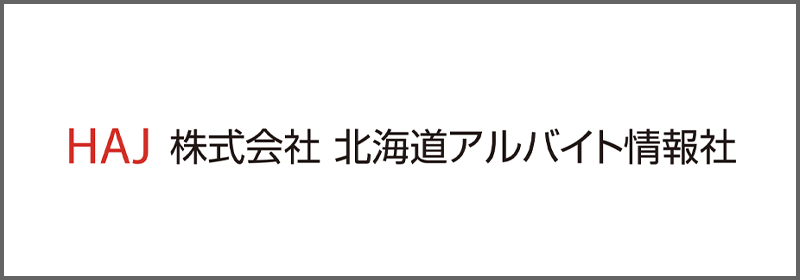「昨日の〇〇さん、ちょっと元気なかったみたいです」
朝の申し送りで、夜勤担当の職員がそう語った。
でも、記録には「異常なし」とだけ書かれていた。
沙耶はその言葉に、記録の“温度差”を感じた。
“異常”ではなく、“変化”が記録されるべきだった。
法人では、福祉サービスの実施状況を記録する体制が整備されていた。
日誌、個別記録、モニタリングシート、電子記録システム。
記録ルールや記載項目も統一されていた。
しかし沙耶は思った。「記録があるだけでは、ケアはつながらない。
“その人の今日”が、次のケアに活かされているかが問われる」
彼女は「記録の質を育てるプロジェクト」を立ち上げた。
目的は、記録を“業務の履歴”ではなく、“ケアの言葉”として共有すること。
まず始めたのは、「気づきの記録欄」の追加。
従来の「対応内容」「体調変化」に加え、
- 表情の変化
- いつもと違う言葉
- 小さな違和感
を記録する欄を設けた。
ある職員はこう書いた。
「佐藤さん、朝の挨拶が少し弱々しかった。
“眠れましたか?”と聞いたら、“まあまあ”と返答。
少し疲れが残っている様子」
この記録が、日中のケアに活かされた。
担当職員は「今日は少しゆっくり過ごしましょうか」と声をかけ、
佐藤さんは穏やかな表情を見せた。
次に、「記録の読み合わせミーティング」を週1回実施。
職員が記録を持ち寄り、「この記述から何が読み取れるか」「次のケアにどう活かすか」を語り合う場。
そこでは、“記録の言葉”が“ケアのまなざし”へと変換されていった。
沙耶はこう語った。
「記録って、“書くこと”より、“読むこと”が大事なんです。
読むことで、ケアがつながる」
さらに、「記録の質向上研修」も実施。
- 事実+感情+関係性の視点で記述する
- “その人らしさ”が伝わる言葉を選ぶ
- 次の職員が“動きやすくなる”記録を意識する
- 記録を“ケアの対話”として捉える
この研修を通じて、記録が“報告”から“共有”へと変化していった。
評価項目【Ⅲ-2-(3)-①――「利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている」。】
それは、「“記録があるか”ではなく、“記録がケアをつなげているか”が問われる。」
沙耶は記録の余白にこう書いた。
「今日、職員が“昨日の記録を読んで、声かけを変えました”と言った。
その一言が、記録共有の成果だと思う」
記録とは、業務の履歴ではない。
それは、“その人の今日”を次のケアにつなげる言葉。
そしてその言葉が、職員間の連携を“関係性の継続”として育てていくのだ。
#福祉サービス第三者評価を広げたい