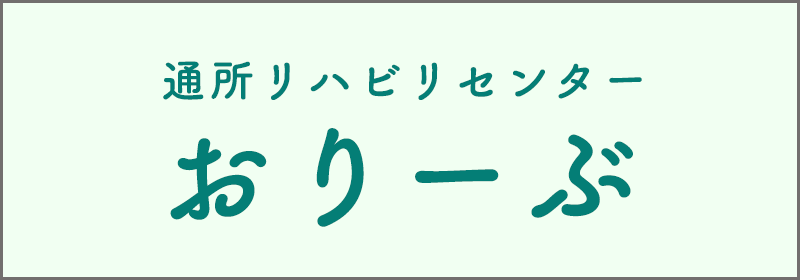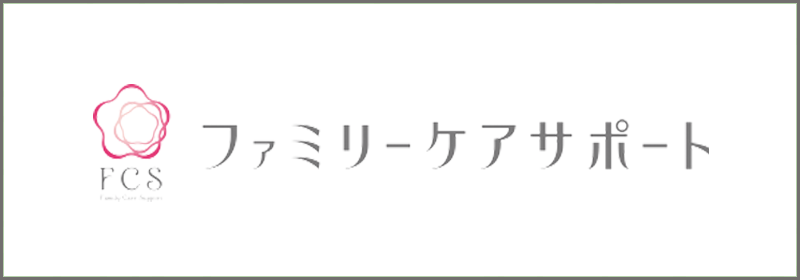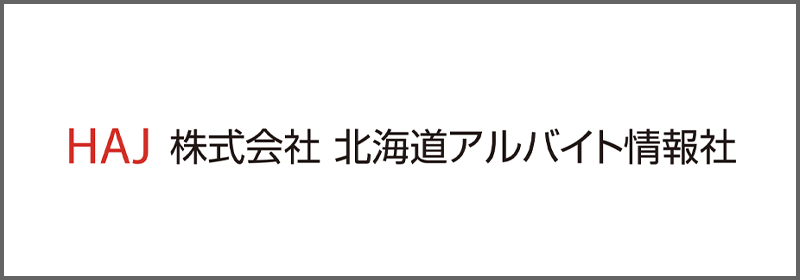「前はできてたことが、最近ちょっとしんどくなってきて…」
利用者の佐藤さんが、ふとした会話の中でそう漏らした。
支援計画には「歩行訓練・週3回」と記載されていたが、
その頻度が、今の佐藤さんには少し負担になっていた。
沙耶はその言葉に、計画の“時間差”を感じた。
“その人の今”に、計画が追いついていない。
計画は、過去の記録ではなく、“今に寄り添う地図”であるべきだった。
法人では、個別支援計画の評価・見直し体制が整備されていた。
半年ごとの定期見直し、モニタリング記録、ケア会議での検討。
しかし沙耶は思った。「定期的に見直していても、“変化の兆し”に応答できているかは別の話」
彼女は「暮らしの再設計プロジェクト」を立ち上げた。
目的は、支援計画を“その人の今”に合わせて柔軟に見直す仕組みを育てること。
まず始めたのは、「変化の気づきメモ」の導入。
職員が日々のケアの中で「以前と違う様子」「新たな希望」「小さな不安」を記録する欄を設け、
それを月1回の「計画ふりかえり会議」で共有するようにした。
ある職員はこう書いた。
「佐藤さん、最近“歩くのが怖い”と口にするようになった。
歩行訓練の前に、安心できる声かけが必要かもしれない」
この気づきが、計画の見直しにつながった。
「歩行訓練・週3回」→「本人の体調と気持ちに応じて、週2〜3回に調整。
開始前に“今日はどうされますか?”と確認する」
次に、「本人参加型の見直し面談」を導入。
半年ごとの見直し時に、利用者本人と職員が一緒に計画を読み返し、
- 今の支援はどう感じているか
- 続けたいこと・減らしたいこと
- 新しく取り入れたいこと
を語り合う時間を設けた。
佐藤さんはこう語った。
「前は“頑張る”って感じだったけど、今は“無理なく続ける”っていう方が合ってる気がします」
沙耶はその言葉に、見直しの本質を見た。
それは、“修正”ではなく、“再設計”だった。
さらに、職員向けに「見直しの質を高める研修」を実施。
- 変化の兆しをどう捉えるか
- 利用者の語りをどう計画に反映するか
- 見直しの目的を“その人の納得”に置くこと
- 計画の更新を“関係性の更新”と捉える視点
この研修を通じて、計画が“紙の記録”から“暮らしの地図”へと変化していった。
評価項目【43 Ⅲ-2-(2)-②――「定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている」。】
それは、「“見直しが行われているか”ではなく、“その人の今に応答できているか”が問われる。」
沙耶は記録の余白にこう書いた。
「今日、佐藤さんが“この計画、今の私にちょうどいいです”と言った。
その一言が、見直しの成果だと思う」
支援計画とは、過去の記録ではない。
それは、“今の暮らし”に寄り添う再設計であり、
その再設計が、ケアの質を“変化に応答する力”として育てていくのだ。
#福祉サービス第三者評価を広げたい