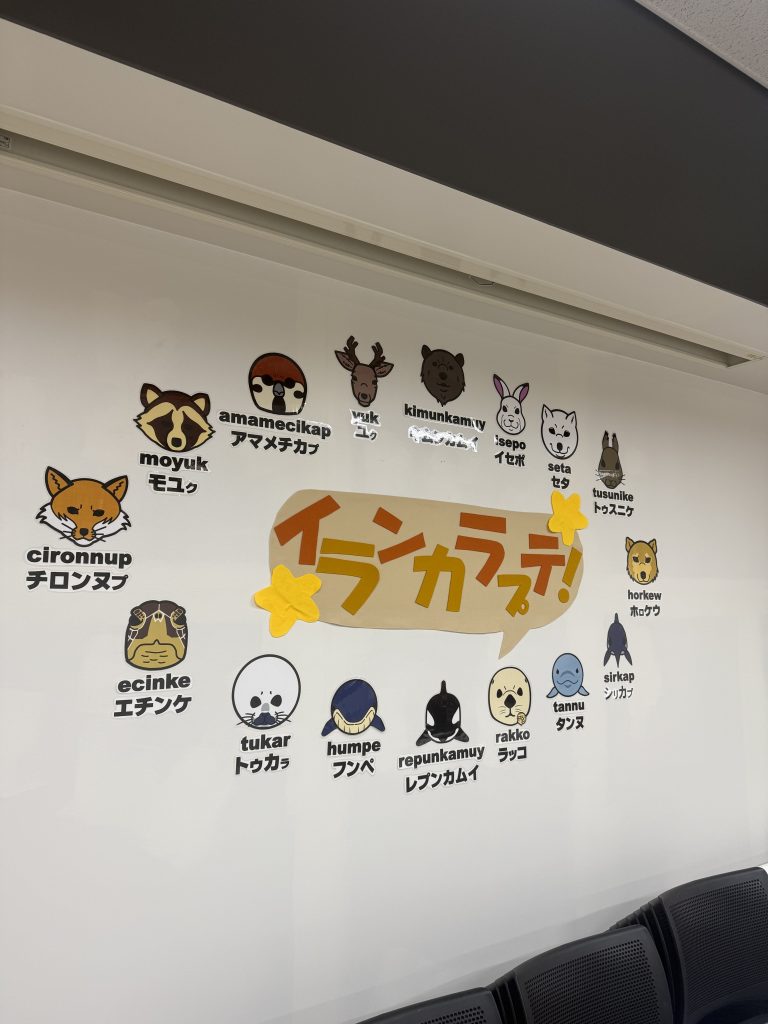介護の現場で日々働く中で、「自分はどんな役割を果たしているのだろう?」「自分の存在がチームや利用者さんにどう影響しているのだろう?」と考える瞬間があるかもしれません。多職種が連携し、利用者さんを支える現場では、全員が重要なピースであり、それぞれの役割には価値があります。しかし、その役割を深く理解し、納得して行動するためには、少しの工夫と哲学的な視点が必要です。ここでは、自分の役割を理解するための方法を哲学的に考えてみましょう。
- 自分の「存在理由」を問い直す
哲学者サルトルは、「人間は自らの生きる意味を作り出す存在である」と語りました。同じように、介護職としての役割の意味も、自ら問い直し、理解を深めることが大切です。
たとえば、「私は利用者さんに何を提供しているのか?」「私の働きがチームにどう影響するのか?」といった問いを持つことで、自分の役割が具体的に見えてきます。食事介助や身体介助といった物理的なサポートだけでなく、笑顔での声掛けや、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢など、自分が提供している価値を振り返り、そこに「存在理由」を見出してみてください。
- チーム全体の中での位置を理解する
哲学者ゲオルク・ヘーゲルは、「全体の中で個々の役割を見つけることが重要だ」と説きました。介護現場もまた、「チーム」という全体の中で成り立っています。自分だけでなく、看護師やケアマネジャー、リハビリスタッフなど他職種が連携する中で、自分の立ち位置を考えることが役割の理解につながります。
たとえば、「私は利用者さんのどんな日常を支えているのか?」「このサポートが他の専門職とどう連携しているのか?」といった視点を持つことで、自分の役割がチーム全体の中でどう貢献しているかが見えてきます。全体を俯瞰する力を養うことで、役割の重要性を再確認できるでしょう。
- 対話を通じて役割を深める
哲学者ソクラテスは、「対話を通じて答えにたどり着く」と考えました。自分の役割を理解するためには、独りで考え込むだけでなく、チームメンバーや先輩との対話が欠かせません。
たとえば、同僚や上司に「自分がもっと力を発揮できる場面はどこだろう?」「他のスタッフから見て自分に期待していることは何だろう?」と率直に聞いてみましょう。周囲の視点を取り入れることで、自分では気づかなかった役割や責任が明確になり、より深い理解につながります。対話を通じて、チームの中での自分の価値を共有することが重要です。
- 小さな役割に「意味」を見出す
哲学者カール・ユングは、「最も小さな行動の中にも深い意味がある」と考えました。介護現場では、掃除や記録、利用者さんへの一言といった日々の小さな行動が、自分の役割に直結しています。
たとえば、「ただの掃除」ではなく「利用者さんが安心して過ごせる環境を作るための掃除」と捉えるだけで、その行動の価値が変わります。一見単純に思える日々の行動も、それがチームや利用者さんにどう影響しているかを考えることで、大きな意味を見出すことができるのです。
- 自分の役割は「変化するもの」と考える
哲学者ハイデッガーは、「人間の存在は常に変化している」と述べました。介護の現場でも、自分の役割は固定されたものではなく、その時々の状況や経験によって変化していくものです。
たとえば、新人の頃はまず基本的な介護業務を担う役割だったかもしれません。しかし、経験を積む中で、後輩を指導する役割や、チームの調整役となる場面も増えてくるでしょう。「役割は成長とともに変わっていく」という視点を持つことで、常に新しい自分を発見することができます。
まとめ
自分の役割を理解することは、介護職としての「存在意義」を見つける旅のようなものです。それは、問い直し、対話し、小さな行動に意味を見出しながら、自分自身を深めていくプロセスです。チームの中での自分の位置や提供できる価値を認識することで、仕事に対するやりがいや充実感がさらに高まるでしょう。